1位
 バイトリル錠(バイロシン)
バイトリル錠(バイロシン)
1箱:1,600円~
2位
 アタキシン錠(バイトリル・ジェネリック)
アタキシン錠(バイトリル・ジェネリック)
1箱:5,800円~
3位
 アシドユリン
アシドユリン
1本:4,100円~
4位
 トキソモックス
トキソモックス
1箱:2,520円~
5位
 リクセン錠600(リレキシペット)
リクセン錠600(リレキシペット)
1箱:2,866円~
▼もっと見る
▼もっと見る
▼もっと見る
▼もっと見る
▼もっと見る
▼もっと見る
▼もっと見る
▼もっと見る
▼もっと見る
▼もっと見る
▼もっと見る
▼もっと見る

猫はおしっこに関わる病気が多く、膀胱に何らかの原因で炎症が生じた状態が膀胱炎です。
膀胱炎は猫がかかりやすい病気の一つでもあります。
そんな膀胱炎を予防する方法あるのか、またかかってしまった時に効くお薬はどんなものがあるのでしょうか。
今回は、猫の膀胱炎や市販薬などについて詳しく紹介していきます!
猫の膀胱炎に効果のある市販薬は、残念ながら存在していないようです。
市販で購入できるものは、尿ケアグッズなどになり、市販薬というものがないです。
猫の膀胱炎治療薬は、海外通販や動物病院を受診して購入するのが一般的な入手法になります。
市販の治療薬を購入するのは難しくても、猫のおしっこの健康をサポートするキャットフードやサプリメントは各メーカーから様々な商品が販売されています。
例えばキャットフードなら、尿ケアや泌尿器サポート等が商品名にあるものなど、市販の尿ケアグッズは多数あります。
最近では猫用のサプリメントなども販売されており、ペットショップや国内の通販サイトなどでも購入できます。
普段からこれらの商品を上手に使い与える事で、膀胱炎の予防や健康サポートに繋げましょう。
猫の膀胱炎の治療薬は、海外通販で入手することが可能です。
膀胱炎の原因は3つほどに分けられますが、それぞれの原因に合わせた数種類の治療薬や、ジェネリックと呼ばれる後発で安価な治療薬も多数存在します。
例えば、バイトリル錠、アシドユリンといった薬は、膀胱炎の治療や尿路結石を除去するための薬で、アタキシン錠はバイトリル錠のジェネリックになります。
種類が豊富なだけでなく、価格面からも飼い主さんが選ぶことができます。
海外通販で購入できる主な猫の膀胱炎治療薬を紹介します。
 |
 |
 |
|
| 商品名 | バイトリル錠 | アタキシン錠 | アシドユリン |
| 有効成分 | エンロフロキサシン | エンロフロキサシン | 塩化アンモニウム |
| 特徴 | ・ペット用のニューキノロン系抗菌剤 ・主に膀胱炎などの治療に使用 |
・バイトリル錠のジェネリック ・同じ用量でも安く購入可能 |
・尿路結石を除去する治療薬 ・結石による膀胱炎に! |
| 価格 | 1箱100錠:5,000円 | 1箱100錠:3,900円 | 1本100錠:3,400円 |
| 購入する | 購入する | 購入する |

市販品の多くは、膀胱炎を治す目的ではなく、あくまでも健康を維持するためのものとして販売されています。
そのため、猫が膀胱炎を発症した時、市販のサプリやフードだけでは治療はできません。
膀胱炎治療を行うためには、海外通販や動物病院で処方されてた治療薬を使用しましょう。
海外通販であれば病院で処方される薬と同じものが購入できるので、市販品よりも確実に治療効果が期待できる薬を見つけられます。
動物病院で診察から治療まで一貫して診てもらうとすると、1回の通院で約7,000~13,000円ほど掛かります。
また症状が落ち着くまでは経過観察が必要で、何度か動物病院に掛かることになり、完治までの治療費も決して安くはありません。
海外通販を利用すると、猫の膀胱炎の薬を動物病院よりも安くまとめ買いできるので、治療コストを大幅に抑えることが可能です。
膀胱炎で動物病院に掛かった一例と海外通販の比較を見てみましょう。
| 動物病院 | 海外通販 ジェネリックを選択 |
|---|---|
| 1年6回通院 35,000円ほど |
1年分の治療薬代 3,900円 |
1年間の治療費として換算すると、海外通販の方が31,000円ほどお得になります。
動物病院の価格が高い理由としては、薬の価格設定が独自でできること、獣医師の診察費が含まれるためです。
長く治療が必要な場合は、海外通販を選ぶことでコストを抑えることができます。
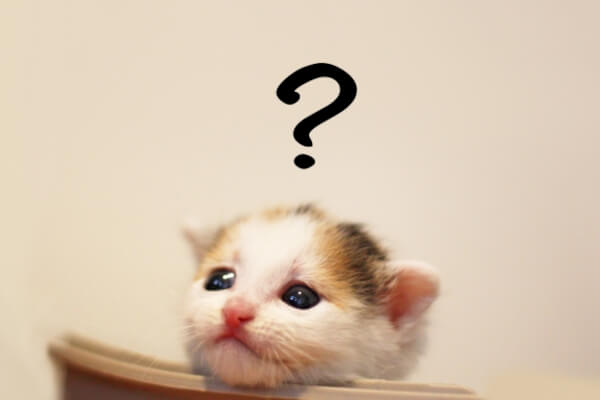
膀胱は、腎臓から送られてきたおしっこを貯めて尿道に排泄する役割があります。
しかし炎症が起きると膀胱が十分に膨らむことが出来ず、また尿道から入った細菌が膀胱まで逆行して炎症を引き起こします。
その結果、頻尿になったりお水を飲む回数が増えたり、排尿時に痛みが生じたりします。
猫の膀胱炎は犬に比べて細菌性の膀胱炎は少なく、原因のわからない猫下部尿路疾患(特発性膀胱炎)が多いという特徴があります。
膀胱炎は繰り返しやすく、軽く考えて様子を見ていると尿道閉塞という、命に関わる状況に陥る事もあります。
また、膀胱炎による排尿障害があると、腎臓病や尿毒症という重大な病気を引き起こす可能性も。
日頃から膀胱炎にならないようケアをするとともに、しっかりと治療を行っていきましょう。
猫の膀胱炎はオスよりも、メスの方が発症しやすいと言われています。
メスは尿道が短く、細菌が膀胱に侵入しやすいため、オスよりも発症しやすいので要注意です。
また、膀胱内の尿血症、尿結石により膀胱の粘膜に傷がつき膀胱炎になるケースもあります。
メスの猫を飼っている方は、毎日の猫の行動をチェックしておきましょう。
膀胱炎が疑われる場合の状態・症状は以下の通りです。
上記のような症状は一度に出るとは限りません。
膀胱炎の程度によって出る症状は異なります。
オスで尿道閉塞がある場合、症状が激しく出るため緊急処置が必要になる場合があります。
膀胱炎の原因になっているものは、大きく分けて以下の3つです。
原因により治療法が異なるため、猫が膀胱炎になった場合はまず原因を特定することが大切です。
ではそれぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
細菌性膀胱炎は大腸菌やブドウ球菌が原因で発症する膀胱炎です。
尿検査により、これらの菌があるかどうか?を検査します。
ブドウ球菌(黄色ブドウ球菌)は皮膚から外陰部へ、大腸菌は便から外陰部へ侵入すると考えられます。
これらの細菌が、外陰部から尿道を伝って膀胱に感染することで発症します。
下痢などにより、体力が弱っている時は特に注意が必要で、オスに比べて、尿路が短いメスの方が細菌感染が起こりやすいと言われています。
膀胱炎=細菌感染と思われていますが、ウイルスや真菌(カビ)によって猫が膀胱炎を発症することは、それほど多くありません。
犬に比べると、細菌性の膀胱炎は猫には少ないようです。

アタキシン錠はバイトリルのジェネリックで、有効成分にエンロフロキサシンを含む膀胱炎の治療薬です。
高い殺菌作用があり、細菌性膀胱炎の治療薬としても使用されています。
| 50mg100錠 | |
|---|---|
| 1箱 | 3,900円 |
| 150mg100錠 | |
| 1箱 | 6,500円 |
何らかの原因でできた結石・結晶が膀胱の粘膜を傷つけることで発症する膀胱炎です。
食事、生活習慣、体質、遺伝的要素など、何らかの原因で尿のpH値が乱れ、尿に溶け込んだ成分に変化し結石ができてしまいます。
膀胱にできた尿結石が膀胱の粘膜を傷つけることで膀胱炎になります。
代表的なものに、ストルバイト結石(=若猫に多い)と、>シュウ酸カルシウム結石(=中高齢の猫に多い)があります。
どちらの結石も、おしっこがアルカリ性に傾くとできやすくなります。
この結石が尿道に詰まると、尿道閉塞(尿道結石)となり、救急処置が必要です。
結石・結晶による膀胱炎の場合は、療法食での治療が一般的となります。
また、一度結石ができた猫は、再発の可能性が高くなります。
尿路結石による膀胱炎は、メス猫よりもオス猫に多く発症します。
これは、メス猫よりもオス猫の方が尿道が細長くカーブを描いている部分があり、さらに先端が細くなっているので、尿道に結石が詰まると重症化しやすいのです。

塩化アンモニウムを含む、尿のpH値を調整するお薬です。
尿の酸性化を防ぎ、尿路結石を予防し、ストルバイト結石を溶解させ除去する効果があります。
| 100mg100錠 | |
|---|---|
| 1本 | 3,400円 |
| 2本 | 6,400円 |
膀胱炎の症状があるのに、検査をしてもはっきりした原因がみつからない場合の膀胱炎に付けられる病名です。
猫の膀胱炎の約半分は、この特発性膀胱炎だと言われています。
比較的、若猫の方が発症しやすいようですが、原因が明らかではないため積極的な診断法は確立されていないようです。
細菌性膀胱炎や結石による膀胱炎を発症して、治療してもなお膀胱炎の症状が続いた場合に、
この特発性膀胱炎が隠れていた、ということもあるようです。
肥満やストレスが原因とも言われますが、はっきりしたことは未だ不明です。
外傷、膀胱腫瘍などでも膀胱炎を発症することもあります。
猫種による発症のしやすさ等はなく、どの猫種でもかかる可能性があります。
動物病院に行ったら基本的に尿検査が行われます。
超音波やレントゲン、血液検査などは尿検査だけでは不確定で、必要に応じて行われます。
もし、猫のおしっこを自宅で取って来るように指示された場合、採取3時間以内、遅くても6時間以内に病院へ持参しましょう。
どうしても自宅で採取できない場合は、無理せず動物病院に相談しましょう。

猫が膀胱炎を発症してしまった場合、原因がわかっているならまずはその原因に対する改善を行います。
それと同時に膀胱内をきれいにするための治療とアフターケアが必要になります。
細菌性膀胱炎の場合は、抗生物質による投薬治療が施されます。
膀胱炎の程度によっては、消炎鎮痛剤が投与される場合もあります。
どちらの場合も、膀胱に溜まっている細菌や結石・結晶をきれいに洗い流すために尿量を増やす必要があります。
飲水量をお家で増やすことが難しい場合、輸液による皮下点滴や膀胱洗浄をすることがありますが、
お家では常にきれいなお水が飲めるような対策が必要です。
原因のわからない特発性膀胱炎の場合は、食事の内容や生活環境を改善しストレス軽減することが治療となる場合があります。
目安となる治療期間ですが、再発する可能性が高い病気であること、膀胱炎の原因によって治療時期に差があることなど、完治までの期間にはかなり幅があります。
特発性膀胱炎の場合は他の膀胱炎とは異なります。
というもの、まず原因が不確定であるため治療法を見つけるまでに時間がかかるケースがあります。
例えば、痛みのある猫には鎮痛剤を投与する、ストレスかも思えばそれを模索しながら排除する、という方法です。
その中で原因を探していく形になります。
目安というと難しいのですが、早ければ2日ほどで改善する猫もいるようです。

猫の膀胱炎は、一度治っても再発しやすい病気です。
そのため、膀胱炎を予防するには食生活の見直しや水分補給を考え、ケアする必要があります。
猫は、普段からあまり水分を摂らない子が多いので、特に飲水量に関しては重要なポイントになります。
猫が1日に必要とする飲水量は、体重1kgあたり40ml程度です。
4kgの猫なら160mlの計算ですが、手作り食やウェットタイプのフードを食べていると、ほとんど水を飲まない猫もいるので注意が必要です。
猫が新鮮な水を、いつでも飲めるようにしておきましょう。
猫が移動する範囲には、猫が飲みたい場所で飲めるようにしておくなど、ちょっと工夫が必要です。
トイレはいつも清潔に保ち、適度に運動させることで水が飲みたくなる環境を整えましょう。
登録時のメールアドレス、パスワードを入力の上、ログインして下さい。
パスワードを忘れた
ログインに失敗しました。
メールアドレス、パスワードにお間違いがないかご確認の上、再度ログインして下さい。
パスワードを忘れた
登録した際のメールアドレスを入力し送信して下さい。
ログインに戻る
あなたへのお知らせ(メール履歴)を表示するにはログインが必要です。
全体へのお知らせは「にくきゅう堂からのお知らせ」をご確認下さい。
パスワードを忘れた
注文履歴を表示するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた
以下の内容で投稿します。よろしければ「送信する」を押して下さい。
以下の内容で送信します。よろしければ「送信する」を押して下さい。
決済が失敗する場合があります。
まれにカード発行会社の規制により、国をまたいだクレジット決済がエラーとなる場合がございます。
クレジット決済ができない場合には、カード発行会社にご連絡いただき、クレジット決済をしたい旨をお伝えいただくことで決済が可能となる場合がございます。
【ご注意ください】
本来、医薬品のクレジット決済はカード規約で禁止されています。
医薬品である旨を伝えてトラブルになったケースもあるようですので、ご連絡される際には「海外の通販サイトを利用したいので制限を解除して欲しい」という旨だけとお伝え下さい。
請求金額が異なる場合があります。
VISA/MASTER/AMEXのカードは元(げん)決済です。
昨今は外貨の変動幅が大きく、元から円へのエクスチェンジ時に為替差益が発生しており、1~2%前後の手数料が掛かっております。
購入金額以外に、この為替差益がお客様の負担となりクレジット会社から請求される可能性がございます。
ご負担頂いた3%分を当サイトでは、次回購入時に利用頂けるポイントとして付与しております。
こちらをご理解の上で、クレジット決済をお願い致します。
※当サイトでは、銀行振込みをオススメしております。